今日のnX-Station
長時間動作による耐久試験継続中。
約一ヶ月連続使用して、サーバ(WindowsXP)の再起動などによる運用停止を除けば問題なかったのだが、本日エラーがでた。
具体的にはブラウザでWebを閲覧中に、突然nX-Stationのファーム画面に切り替わり、英語で「サーバと接続できなくなったので、ちょっとしてから再度接続しなおしてくれ、データは保存されているよ」といった内容が表示。
すぐに再接続するも、同じ画面で停止。
しばらくして接続すると、今度は先ほどのブラウザ画面が帰ってきた。
サーバ側かネットワークになんらかのレスポンス異常でもあったのだろうか。
表示からは読み取ることができなかった。
約一ヶ月連続使用して、サーバ(WindowsXP)の再起動などによる運用停止を除けば問題なかったのだが、本日エラーがでた。
具体的にはブラウザでWebを閲覧中に、突然nX-Stationのファーム画面に切り替わり、英語で「サーバと接続できなくなったので、ちょっとしてから再度接続しなおしてくれ、データは保存されているよ」といった内容が表示。
すぐに再接続するも、同じ画面で停止。
しばらくして接続すると、今度は先ほどのブラウザ画面が帰ってきた。
サーバ側かネットワークになんらかのレスポンス異常でもあったのだろうか。
表示からは読み取ることができなかった。
2005,12,06 Tue 04:24
Thinクライアントを検証してみる
ブロードバンドが普及しPCが多機能多様化してくると、決まって「情報弱者はどうするのか」「高額化するコストをどうするのか」といった問題がでてくる。
そのための「誰でもが簡単に使えるネットワーク端末」は伊那EC実験の頃の日本電算機のiBoxや映像用セットトップボックスなど取り組んできたが、どれも結論的には「PCには叶わないよね」というのが(特にPCユーザーからの)結論になってしまっているようだ。
そういった経過からも以前から「Thin(しん)クライアント」という考え方には興味があった。
Thinクライアントとは、映像出力・キーボードマウス入力と、ホストとなるPCとの通信のためのインターフェースと処理機能のみを持たせたネットワーク端末の総称である。
Thinクライアントの特徴として
・ホストPCの機能をそのまま使うことができる
・端末装置の構成が簡単なので安価
・端末装置に余計な入出力を持たないので安定している
・同上の理由によりセキュリティも高い
・ディスプレイやキーボード・マウスなどはPCのものをそのまま使える
といった点が挙げられる。
Thinクライアント自体の概念は以前から存在していたのだが、これを実現するには
・ホストPCの高性能化
・ネットワークの高速化
・製造コストの低廉化
が必須であり、これに技術的な問題も加わって今まで表舞台にでてくることは少なかった。
ところがエルザよりthinクライアントがでるという情報を聞いた。販売はアスクからで価格は25000円台とのこと。
どちらもPCパーツでは名の通った会社だが、「PCに接続するネットワーク端末」といったイメージだろうか。
同社のwebなどをみると、家庭内や企業内で使用することをイメージしているようである。これを地域ネットワークで使用するとどのような利用や問題点がでてくるのであろうか。
そこで、伊那市有線放送農業協同組合(いなあいネット)さんとアスクの深江さん、エルザの川崎さんのご協力を得て、地域情報化の観点でThinクライアントを検証してみようと計画してみた。
特に地域における遠隔医療のツールとして有効ではないかと考えているのだが・・・次回から詳細。

nx-station
続き▽
そのための「誰でもが簡単に使えるネットワーク端末」は伊那EC実験の頃の日本電算機のiBoxや映像用セットトップボックスなど取り組んできたが、どれも結論的には「PCには叶わないよね」というのが(特にPCユーザーからの)結論になってしまっているようだ。
そういった経過からも以前から「Thin(しん)クライアント」という考え方には興味があった。
Thinクライアントとは、映像出力・キーボードマウス入力と、ホストとなるPCとの通信のためのインターフェースと処理機能のみを持たせたネットワーク端末の総称である。
Thinクライアントの特徴として
・ホストPCの機能をそのまま使うことができる
・端末装置の構成が簡単なので安価
・端末装置に余計な入出力を持たないので安定している
・同上の理由によりセキュリティも高い
・ディスプレイやキーボード・マウスなどはPCのものをそのまま使える
といった点が挙げられる。
Thinクライアント自体の概念は以前から存在していたのだが、これを実現するには
・ホストPCの高性能化
・ネットワークの高速化
・製造コストの低廉化
が必須であり、これに技術的な問題も加わって今まで表舞台にでてくることは少なかった。
ところがエルザよりthinクライアントがでるという情報を聞いた。販売はアスクからで価格は25000円台とのこと。
どちらもPCパーツでは名の通った会社だが、「PCに接続するネットワーク端末」といったイメージだろうか。
同社のwebなどをみると、家庭内や企業内で使用することをイメージしているようである。これを地域ネットワークで使用するとどのような利用や問題点がでてくるのであろうか。
そこで、伊那市有線放送農業協同組合(いなあいネット)さんとアスクの深江さん、エルザの川崎さんのご協力を得て、地域情報化の観点でThinクライアントを検証してみようと計画してみた。
特に地域における遠隔医療のツールとして有効ではないかと考えているのだが・・・次回から詳細。

nx-station
続き▽
2005,11,04 Fri 06:02
災害時に非接触ICカードを使ってデータベースをつくることについて
ITメディアの速報。
論文のほうも読みましたが、なかなか奇特なことを考える人もいるなぁという感。
すでに流通している非接触ICカードったって、おサイフケータイとかスイカ・イコカですよねぇ。
使える場所が少ないので持っている人が少ない伊那のような田舎は問題外みたいです。
総務省が発行している住民基本台帳カードは、伊那地域では4%と大変普及しているそうだが、このICカードは接触型。つまりは普及している非接触カードではないということ。
どうも大阪の人らしく都市型災害対策を念頭に書かれているようだが、読み取ったデータを格納するデータベースやら災害は広域に及んだ場合、都市と地方、非接触ICカードの実際などさらに検証が必要なことが多すぎる。
それよりは災害に強い携帯電話システムを考察・・・というより構築してしまったほうが実効性が高いだろう。
きっとこういう議論って役所がデータベースをつくることだけが主眼になるのではないかな。
論文のほうも読みましたが、なかなか奇特なことを考える人もいるなぁという感。
すでに流通している非接触ICカードったって、おサイフケータイとかスイカ・イコカですよねぇ。
使える場所が少ないので持っている人が少ない伊那のような田舎は問題外みたいです。
総務省が発行している住民基本台帳カードは、伊那地域では4%と大変普及しているそうだが、このICカードは接触型。つまりは普及している非接触カードではないということ。
どうも大阪の人らしく都市型災害対策を念頭に書かれているようだが、読み取ったデータを格納するデータベースやら災害は広域に及んだ場合、都市と地方、非接触ICカードの実際などさらに検証が必要なことが多すぎる。
それよりは災害に強い携帯電話システムを考察・・・というより構築してしまったほうが実効性が高いだろう。
きっとこういう議論って役所がデータベースをつくることだけが主眼になるのではないかな。
2005,09,10 Sat 06:11
エディを入手
先日ICカードについて書いたが、そのひとつである「Edy」はかなり身近になってきている。
EdyはICカードの規格ではない。
規格ではFelicaというソニーが開発した・・・だったかな・・・非接触ICカードを利用した電子マネー決済システムをEdy(エディ)と呼ぶ。
これを携帯電話に載せたのが、最近よく聞く「おサイフケータイ」である。
簡単に言えば、ケータイにFelicaチップを搭載して、Edy機能を持たせたということになるが、おサイフケータイの素晴らしいところは、Edyでもいーなちゃんカードでも共通して言える問題点、「電子マネーをカードに覚えさせたりする」ことが携帯でできてしまう点にある。
従来のICカード型電子マネーは、この「チャージ」と呼ばれるお金情報を入力するために専用端末機を必要とする。
いーなちゃんカードでは店頭端末機で入金する。
Edyも店頭でできる他に、専用ICカードリーダをパソコンにつないでインターネットからでもできる。
Edyと同じFelica規格をつかっているJR東日本のSUICAは駅の発券機で入金する。
いずれも他人、ないしは若干の手間暇をかけないと、タッチアンドゴーや釣り銭なしのスマート決済という電子マネーのメリットが生かせないのだ。
ところがおサイフケータイは携帯アプリを使ってチャージ(入金)してしまい、その費用は携帯電話の月々の電話料と合算して請求される。つまり携帯の簡単な操作だけで入金もできるし、またはアプリを組み合わせたより高度で便利なサービスを組み合わせることができるのである。
強いて言う問題点は、おサイフケータイ対応携帯の種類が少ないことや、携帯の機種変更というのは最近ではなかなかできないので入手しずらい点にあるが、最近Edy決済をするだけの非接触ICカードが簡単に手に入る場所を見つけた。
それはサークルK。そうあのコンビニで、値段は300円である。
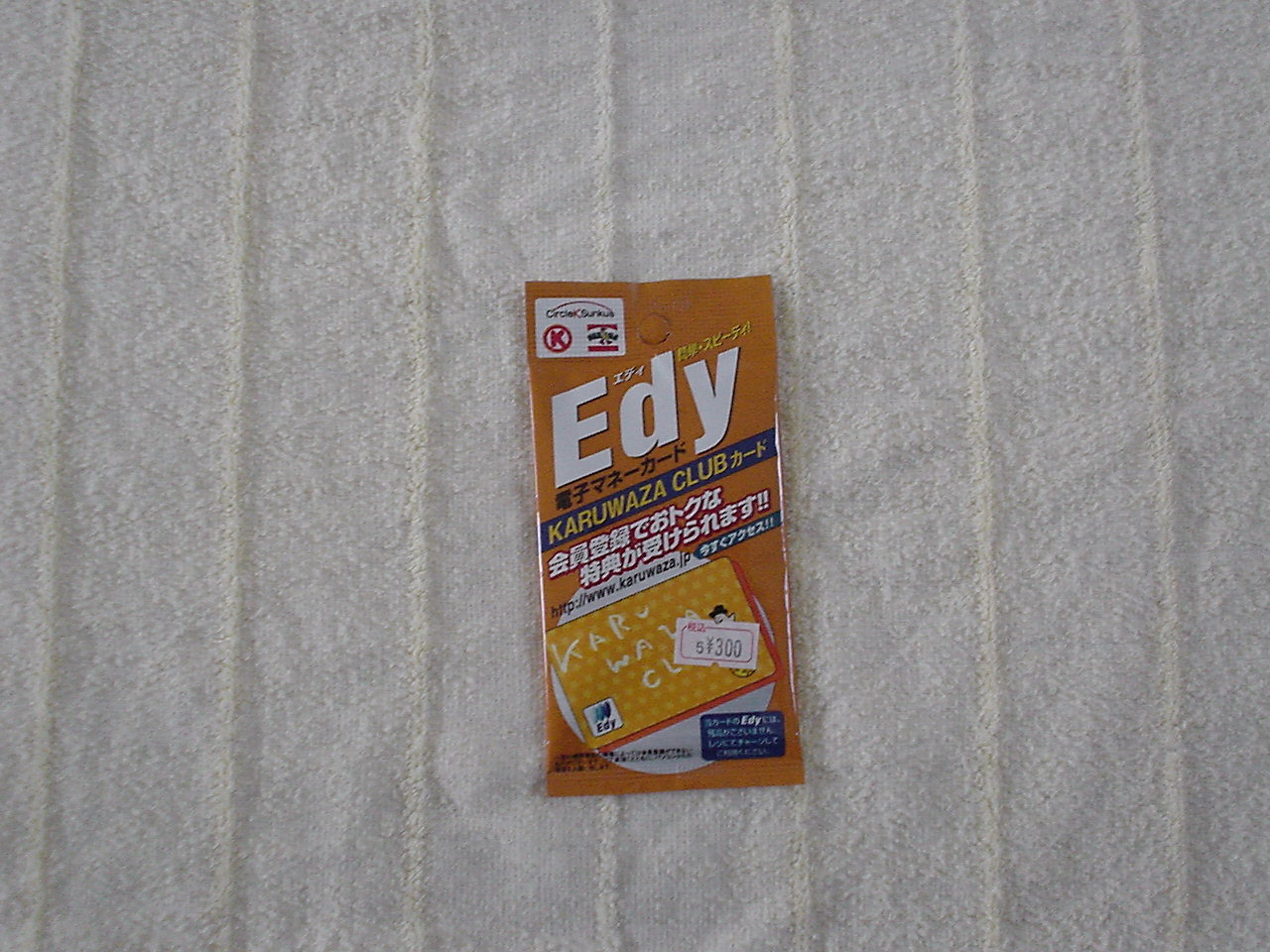
私は仕事で、この非接触ICカードを単体で購入したことがあるが、単価としてはとても300円で買えるものではなかった。それが集客目的での店頭販売としても300円で精密最新技術が買えるとは・・・・。
いい世の中になったものである。
EdyはICカードの規格ではない。
規格ではFelicaというソニーが開発した・・・だったかな・・・非接触ICカードを利用した電子マネー決済システムをEdy(エディ)と呼ぶ。
これを携帯電話に載せたのが、最近よく聞く「おサイフケータイ」である。
簡単に言えば、ケータイにFelicaチップを搭載して、Edy機能を持たせたということになるが、おサイフケータイの素晴らしいところは、Edyでもいーなちゃんカードでも共通して言える問題点、「電子マネーをカードに覚えさせたりする」ことが携帯でできてしまう点にある。
従来のICカード型電子マネーは、この「チャージ」と呼ばれるお金情報を入力するために専用端末機を必要とする。
いーなちゃんカードでは店頭端末機で入金する。
Edyも店頭でできる他に、専用ICカードリーダをパソコンにつないでインターネットからでもできる。
Edyと同じFelica規格をつかっているJR東日本のSUICAは駅の発券機で入金する。
いずれも他人、ないしは若干の手間暇をかけないと、タッチアンドゴーや釣り銭なしのスマート決済という電子マネーのメリットが生かせないのだ。
ところがおサイフケータイは携帯アプリを使ってチャージ(入金)してしまい、その費用は携帯電話の月々の電話料と合算して請求される。つまり携帯の簡単な操作だけで入金もできるし、またはアプリを組み合わせたより高度で便利なサービスを組み合わせることができるのである。
強いて言う問題点は、おサイフケータイ対応携帯の種類が少ないことや、携帯の機種変更というのは最近ではなかなかできないので入手しずらい点にあるが、最近Edy決済をするだけの非接触ICカードが簡単に手に入る場所を見つけた。
それはサークルK。そうあのコンビニで、値段は300円である。
私は仕事で、この非接触ICカードを単体で購入したことがあるが、単価としてはとても300円で買えるものではなかった。それが集客目的での店頭販売としても300円で精密最新技術が買えるとは・・・・。
いい世の中になったものである。
2005,08,24 Wed 00:35
地上波デジタルやらCATVやらコミュニティFMやら
最近地元ケーブルテレビの東京波の画像が乱れがちになってきた。
と思ったらケーブルテレビさんによると、今まで実験でやってきたが元に戻したいったような説明が独自放送のところどころにでるようになった。
けど、視聴者にはなんのことだかわからないのが実際。
私も当事者ではないのでよくわからないのだが、ちょっと調べてみると地上波アナログ放送の再送信問題というのは、特にケーブルテレビさんにおいては全国いろいろと問題をかかえているようだ。
地元、特に視聴者の要望で阪神戦を見たいためとか、東京のキー局をみたいとかでがんばろうとするケーブルテレビと、地元テレビ放送局へ有料で配信しているキー局、それを管轄する総務省・・・・その中でいろいろとやりあっているというのが現状か。
参考
ところで国、というか総務省が最終的にアナログ放送を止めてまで進めようとしている地上波デジタル放送、これが再送信問題に決着をつけることになるかもしれないというのが最近の見方。光ネットへの再送信といったことへの対応によって、今までうやむやだった部分を明確にしようということだろうか。
となると、地方のケーブルテレビ局は阪神戦や東京キー局の再配信ができなくなる可能性があるわけで、以前から地上波デジタルを脅威と考えて、地上波デジタル対応の設備に切り替えているところが増えてきているようだ。でも、これってやはりタコが足食うような話で地方のケーブルテレビに過大な設備投資を強制させて経営を弱体化させるばかりか、視聴者にはわかりにくい無駄な投資と思われがちになる。
伊那市でも以前から検討されているコミュニティーFMにしてもそうだが、地元・地域の有利性を最大限に生かしていくことしか、地元密着型メディアやら情報基盤やらの存続の意味は、グローバルネットワークと技術革新の時代には残されていない。伊那市有線放送農協の半世紀の歴史やらを見直すと、技術の違いはあれど明かである。
国の動向や周辺がやっているからうちもと簡単に飛びつくのもある意味では必要なことはあるのだが、それを短期間に繰り返しているのでは所詮地方の無駄づかいと言われかねない。
「器つくって魂入れず」なマルチメディア・IT施設が多く存在する今日において、これらの地域型メディアにはぜひ、再度地域を見直してそれに似合った技術を適用することをおすすめしたい。
ところで同郷に素晴らしいblogを発信している方をみつけた。コメントも素晴らしいしwebデザインも秀逸。勝手にトラックバックをはらせていただくが、こういう方々をもっと地域メディアにアイデアやコンテンツを提供してもらうなど、協力してもらえる受け皿をつくってみてはいかがだろうか。
と思ったらケーブルテレビさんによると、今まで実験でやってきたが元に戻したいったような説明が独自放送のところどころにでるようになった。
けど、視聴者にはなんのことだかわからないのが実際。
私も当事者ではないのでよくわからないのだが、ちょっと調べてみると地上波アナログ放送の再送信問題というのは、特にケーブルテレビさんにおいては全国いろいろと問題をかかえているようだ。
地元、特に視聴者の要望で阪神戦を見たいためとか、東京のキー局をみたいとかでがんばろうとするケーブルテレビと、地元テレビ放送局へ有料で配信しているキー局、それを管轄する総務省・・・・その中でいろいろとやりあっているというのが現状か。
参考
ところで国、というか総務省が最終的にアナログ放送を止めてまで進めようとしている地上波デジタル放送、これが再送信問題に決着をつけることになるかもしれないというのが最近の見方。光ネットへの再送信といったことへの対応によって、今までうやむやだった部分を明確にしようということだろうか。
となると、地方のケーブルテレビ局は阪神戦や東京キー局の再配信ができなくなる可能性があるわけで、以前から地上波デジタルを脅威と考えて、地上波デジタル対応の設備に切り替えているところが増えてきているようだ。でも、これってやはりタコが足食うような話で地方のケーブルテレビに過大な設備投資を強制させて経営を弱体化させるばかりか、視聴者にはわかりにくい無駄な投資と思われがちになる。
伊那市でも以前から検討されているコミュニティーFMにしてもそうだが、地元・地域の有利性を最大限に生かしていくことしか、地元密着型メディアやら情報基盤やらの存続の意味は、グローバルネットワークと技術革新の時代には残されていない。伊那市有線放送農協の半世紀の歴史やらを見直すと、技術の違いはあれど明かである。
国の動向や周辺がやっているからうちもと簡単に飛びつくのもある意味では必要なことはあるのだが、それを短期間に繰り返しているのでは所詮地方の無駄づかいと言われかねない。
「器つくって魂入れず」なマルチメディア・IT施設が多く存在する今日において、これらの地域型メディアにはぜひ、再度地域を見直してそれに似合った技術を適用することをおすすめしたい。
ところで同郷に素晴らしいblogを発信している方をみつけた。コメントも素晴らしいしwebデザインも秀逸。勝手にトラックバックをはらせていただくが、こういう方々をもっと地域メディアにアイデアやコンテンツを提供してもらうなど、協力してもらえる受け皿をつくってみてはいかがだろうか。
2005,08,15 Mon 06:16